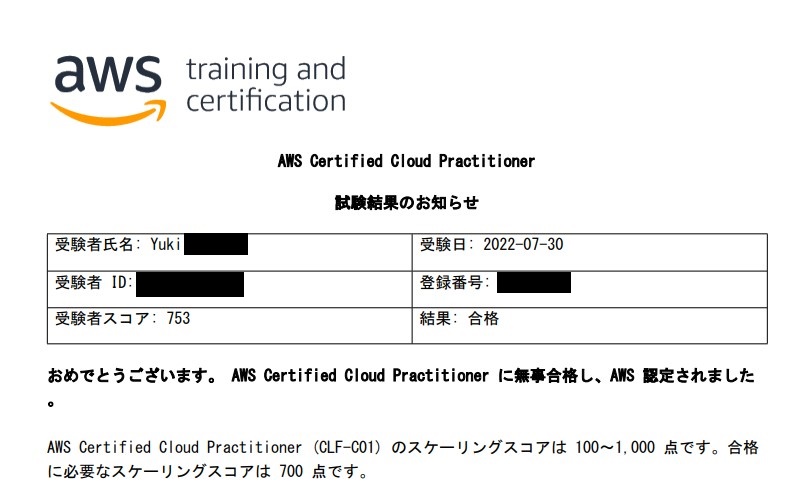とある配信を見ていて、Youtubeの活動方針とかとか色々会話されてるのを見て、僕もYoutuberを名乗っているわけではないのですが、動画を投稿する側です。Youtubeとの付き合いは長いですが、Youtubeと真面目に向き合ったことはありませんでした。今日は、僕とYoutubeの関係と、向き合い方について書いていこうと思います。
Youtubeと最初の出会い
僕が最初にYoutubeを知ったのは、Youtubeが日本語に対応する直前くらいの2007年でした。この頃はFlash全盛期で、動画と言えばFlashでした。Youtubeの誕生はかなり革新的な出来事でした。ネットでも話題になり、さっそくアカウントを作って、適当に動画を撮ってアップロードしてみました。(後ほど説明しますが、僕の動画はこの動画以外は全て無編集です)
車載動画にした理由ですが、車の運転状態を保存したかったからです(つまりドラレコ)。
今でこそ新車を買えばオプションでドラレコをつけれたり、標準でついてたりしますが、2007年はまだドラレコが一般的ではありませんでした。運転中の動画を常に記録すれば、事故った時に絶対に役立つから、ドラレコは流行るだろうと思いました。15年もかかりましたが、最近はドラレコ搭載が増えていて、僕の予想はあたったようで、何よりです。
この件に限らないし、自分で言うのもあれなんですが、そこそこ先見の明はあると思ってますw
Youtubeをどう活用していくか(2007)
僕は、このYoutubeというサービスを使って自分に何が出来るのだろうと考えました。当時アップロードされてる動画は海外の外国人が撮影した外国のものばかり。内容もみんなバラバラで、子供の動画だったり飼い犬の動画だったり。みんなが試行錯誤していました。
最初の動画を投稿したあとに、以下の3つが課題だと考えました。
- Youtubeの存在自体、IT系技術者やITに興味がある人しか知らない。
- 日本人のYoutube視聴者が全然いない。
- 動画の編集は大変過ぎる。
それぞれに答えがあります。
1は、自分一人では無理なので考えないことにします。
2ですが、それならば、動画の対象を外国人にすれば良いのです。さらに、僕には子供の頃に習ってた、全世界共通で楽しめる音楽(ピアノ)という武器がありました。音楽なら言語は関係ないので2は解決できます。曲も、世界の人が知っていそう&クラシック音楽以外&曲名に日本語を含まないことで、外国人の視聴者が見込めます。
3ですが、2007年当時は動画の編集を家庭用のPCでするのは普通ではなく、動画編集ソフトもプロ向けしか無かったり、動画編集するにしてもPCのスペックが全然足りなかったりで、編集がとても難しい状態でした。そこで僕が採った案は「編集しない」です。
以上から、Youtubeの活用方法は「ピアノの演奏動画をインターネット上に公開しつつ、それを記録とする」でした。
以下の動画は僕がピアノを弾いた動画で、”Angel’s fear”という曲です。スーパーファミコンで発売された「聖剣伝説3」のBGMとして使われている曲です。聖剣伝説3は”Seiken Densetsu 3″という名前で海外でも発売されていたようで、このゲームをやったことがある人であれば絶対に知っている曲です。説明欄に英語で「この曲のピアノパートだけを弾きました。もしギターが弾ければなぁ…」という内容を書いています。
僕の憶測は当たり、15年前に投稿したピアノ動画は、英語のコメントで埋まり、たくさんの方にご視聴いただきました。
その後、Youtubeが日本語化されニコニコ動画が台頭してきます。ニコ動も動画投稿サイトですが、動画上にコメントを流せるシステムがあります。これが非常に好評で、体感ですが2007~2009年くらいをピークにYoutubeよりニコ動が主流だった時代があったと思います。当時の僕は大学生だったのですが、友人との会話もニコ動の話ばかりでした。
2011年に大学を中退した僕は、家庭のこと、僕の体のこと、仕事のことなど、ごたごたあり、5年前くらいまではほとんど動画を投稿していませんでした。
ちょうど、僕が30歳の時に普通自動二輪の免許を取り、バイクを買いました。バイクはドラレコがついてなかったので、ヘルメットにカメラをマウントさせています。ここで僕のYoutubeの活用方法が「ピアノの演奏動画をインターネット上に公開しつつ、それを記録とする」から「バイクで撮った動画で共有したいと思った動画もアップロードする」に変わりました。
ちょっと昔話をさせてください!
僕が中学生の時の話です。僕の実家の近くには1kmちょいの長い橋があります。道路は歩行者・自転車が通れる歩道と、片側一車線の道路です。

ここを自転車で走っていたのですが、道路上に落下物があったんです。具体的に何が落ちてたいのかは忘れてしまいましたが、大きなアルミ片か何かだったと思います。少し反対車線に避ければ通れるので、ほとんどの車は落下物を避けて通っていました。
「この落下物は俺が片付けなかったら、誰がやるんだろう?恥ずかしいけど、片付けるか。」
自転車を脇に止めて、縁石の上に立って落下物を避けて通る車の列が切れるのを待ちました。なかなか切れないなーと思っていたら、大型トラックを運転していた方が完全に停止して、パッシングしてくださったんです。当時中学生の僕は免許を持っていませんが、親が運転する車の助手席はよく乗っていたので「パッシング=譲る」という意味は知っていました。
なので、道路に立ち入って問題ない状況と判断して、道路に入り落下物を歩道に移動させました。
トラックは僕が歩道に戻ったのを見て、動き出しました。去り際にトラックの運転手が今度はホーンを鳴らしてくれたんです。これは、サンキューを意味するホーンかと理解した瞬間、最高に嬉しくて感動しました。嬉しすぎてしばらく動けなかったです。
この出来事は今でも鮮明に覚えています。そして、この時から僕の「人生で絶対に守ること」リストの中に、「道路上に落下物があったら可能な範囲で片付ける」が加わりました。これは親から学んだ「肘をつきながら食事をしない」と同レベルの「人生で絶対に守ることリスト」です。
なので、僕のチャンネルで公開しているバイク関連の動画は落下物を拾った系の動画がいくつかあります。他にも「右折時にスポーツカーが教習車両ばりの右寄せしててカッコイイ」とか、「都庁の駐輪場が迷路」とかそんな動画を上げています。
Youtubeをどう活用していくか(2022)
話をYoutubeに戻します。最近は雑多な内容の動画ばかりアップロードしています。2進数から10進数への変換方法とか、ネットワークの試験が新しくなって範囲が広がったねとか航空無線通信士の実技試験の勉強動画とか、とか。
ここまでの現状から、改めてYoutubeをどう活用していくか投稿者視点で考えていきます。
- 収益化はしない
- 仕事ではなく趣味の一つとして継続する。
- 対価(お金)を頂けるほどのコンテンツを作るスキルが無い。
- 記録的な意味で車載動画やピアノ動画を上げる。
- 自分が見たい動画が無い&作れそうなら、自分で動画を作って投稿する。
- 僕が調べて見つからないということは、需要があるのに動画(供給)が無いということなので、同じ動画探しをしてる人は僕以外にもいるはず。
その人達のためにも、自分で出来る範囲なら動画を投稿する。
自分も良くて他人も良い、Win-Winです。
ちなみに、航空無線通信士の動画はまさに、需要があるのに供給が無かった動画なので、僕のチャンネルでは珍しく、1万再生を超えています。それだけ需要があったってことですね。
- 無編集は継続する
- 編集作業は時間がかかる
- 2007年と比べれば編集は簡単になったと思うので、新しくトライしてみても良いかも。
- 動画編集は趣味ではないが、簡単に字幕を入れるくらいは出来るようになりたい
- もちろん冗談ですが、動画編集に関しては、お金払ってでも良いから現役のJK, JCから教えて欲しいくらい。彼女らは最新技術の取り入れ力と、取り入れた最新技術を応用する能力に秀でてますね。。
- そもそも少し雑音が入った無編集動画の方が個人的に好き
こんな感じかな。
長くなってしまいましたが、今日はここまでにしておきます。視聴者目線でYoutubeをどう付き合っていくか、についても書きたいですね。
余談:少し自慢してもいいですか?
上の、「指輪の外し方(紐を使って) How to take off a ring if it’s too tight」は、2010年に僕が投稿した動画で、僕の投稿した動画の中では最も多い10万再生を超えています。
こんなに再生されたのは、3つ理由があると思っています。
- 例えば日本語で「指輪 外し方」で検索をしても、日本語で紐を使った方法の動画が存在しなかった
- タイトルに英語を併記することで、対象を日本人だけではなく外国人も視聴対象とした
- 動画を投稿した2010年当時はタイトルを自動で日本語に翻訳する機能が無かった
3の話になるのですが、2010年のYoutubeは動画のタイトルを自動で日本語に翻訳する機能がありませんでした。当時の検索アルゴリズムは分かりませんが、2010年は検索に引っかかりやすいようにタイトルに日本語の英訳を入れました。それが功を奏したのか、過去一の視聴回数になっています。
この余談、ちょっと面白い後日談がありますw
動画を投稿した2010年から何年か後に、僕の母親も「指輪の外し方」でYoutube検索をかけて、外れなくなった指輪を外したらしいのですが、その時に見た動画がまさにこれだったそうですw
母は僕のYoutube活動を全く知らないし、この動画は北海道で一人暮らしをしてる時に撮った動画なので、「この動画で俺が投稿した動画ってよく分かったな!?」って聞いたら、後ろのオブエジェクトのような温度計が北海道に引っ越す前に実家にあったので、それが気になりポイントだったそうです。
まさか僕が投稿した動画が、母親に伝えたわけでもなく、母親はそもそもYoutubeのアカウントを持ってなくて僕のチャンネルをフォローしてるとかが無いので、本当にたまたま僕の動画が見つかったのは凄いのと、温度計からもしかして息子の動画・・・?って紐づけた母も凄いです。