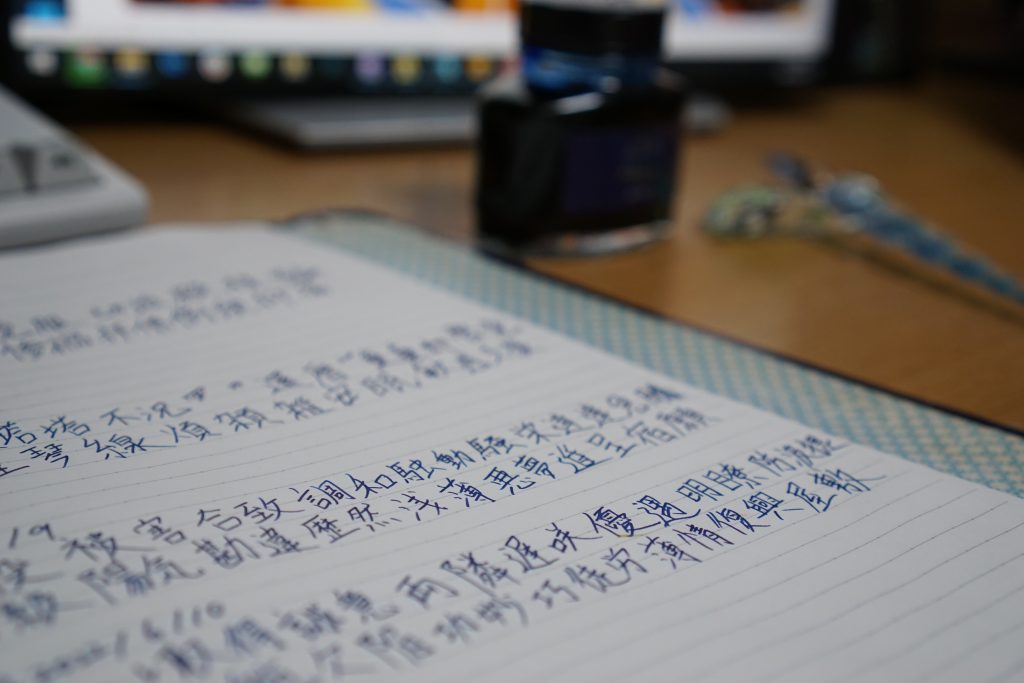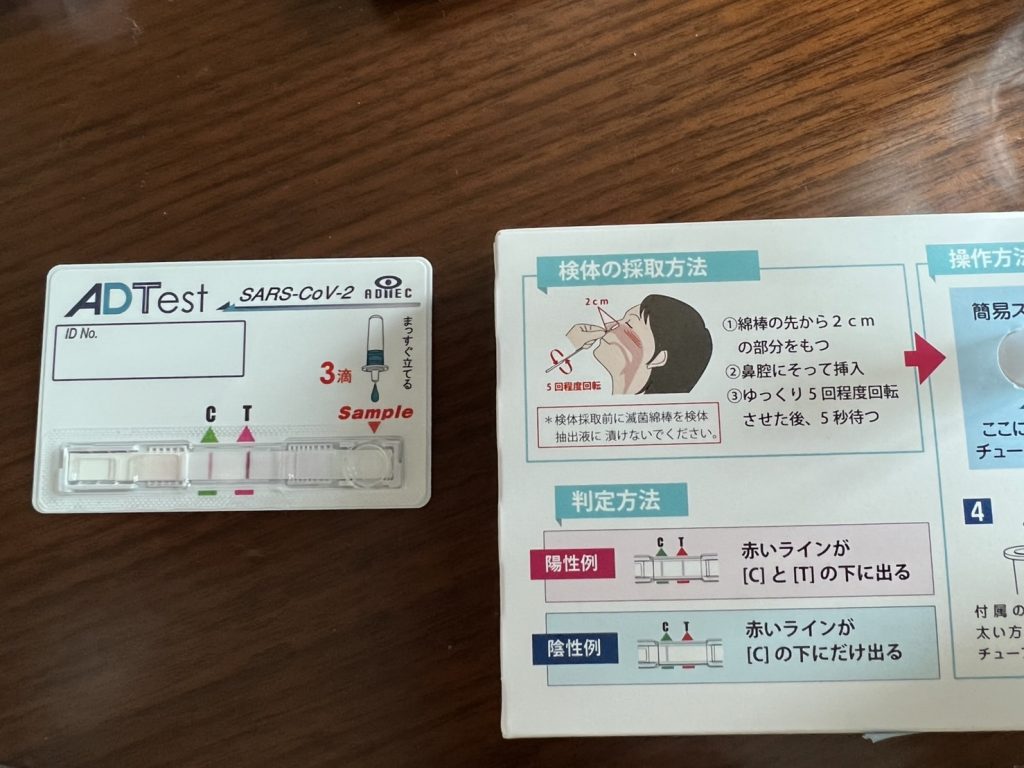特にきっかけは無いのですが、レコードプレーヤーが欲しくなって買いました。最初はスピーカー内蔵のプレーヤー(ION Max LP)を買って使ってたのですが、クラシック(特にオーケストラ)を聞くときに細かい音がもっと鮮明に聞きたくてDenon DP-29Fを買いました。
ION Max LPはアンプ内蔵型だったので、スピーカーと繋ぐだけで良かったのですが、Denonのプレーヤーはアンプが内蔵されてないので、フォノプリアンプとパワーアンプも買いました。パワーアンプは、名前の響きからレコードの針から取れる小さな音を増幅するのかなと思ってたのですが、レコードって低音は音量を下げて盤面に記録してるんですね。それを元の音に直すのがフォノプリアンプで、レコードを聞くには必須の機材でした。レコードを触ったのも初めてで、何かもが初めてで、とても勉強になりました。
先程、「細かい音」が聞こえるという抽象的な表現で書きましたが、実際にどういう音が聞こえるかというと、オーケストラを聞くとバイオリンとかフルートとかの中に、チェンバロやトライアングルの音が聞こえるんです。「CDでも聞こえるよ!」って意見はあると思うのですが、個人的にオーケストラはレコードの方が色々な音が聞こえて良いなと思いました。
逆にピアノ曲は、僕がピアノを習っていたせいなのか、耳がそこまで肥えてないせいなのか分かりませんが、CDで聞くのと違いが分かりませんでした。昔の邦楽も同様に違いが分かりませんでした。なので、クラシックの中でもオーケストラを聴いてます。
最近はレコードブームというのもあり、近所のハードオフに行くとたくさんレコードが並んでるので、適当に買っては家で聞いてみて、良かったらキープ、微妙と思ったらまたハードオフに売りに行くということを繰り返してます。